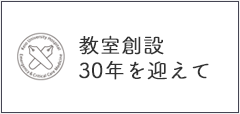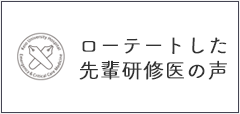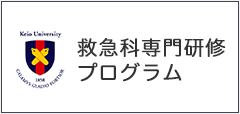救急医療は「セーフティー・ネット」の一部
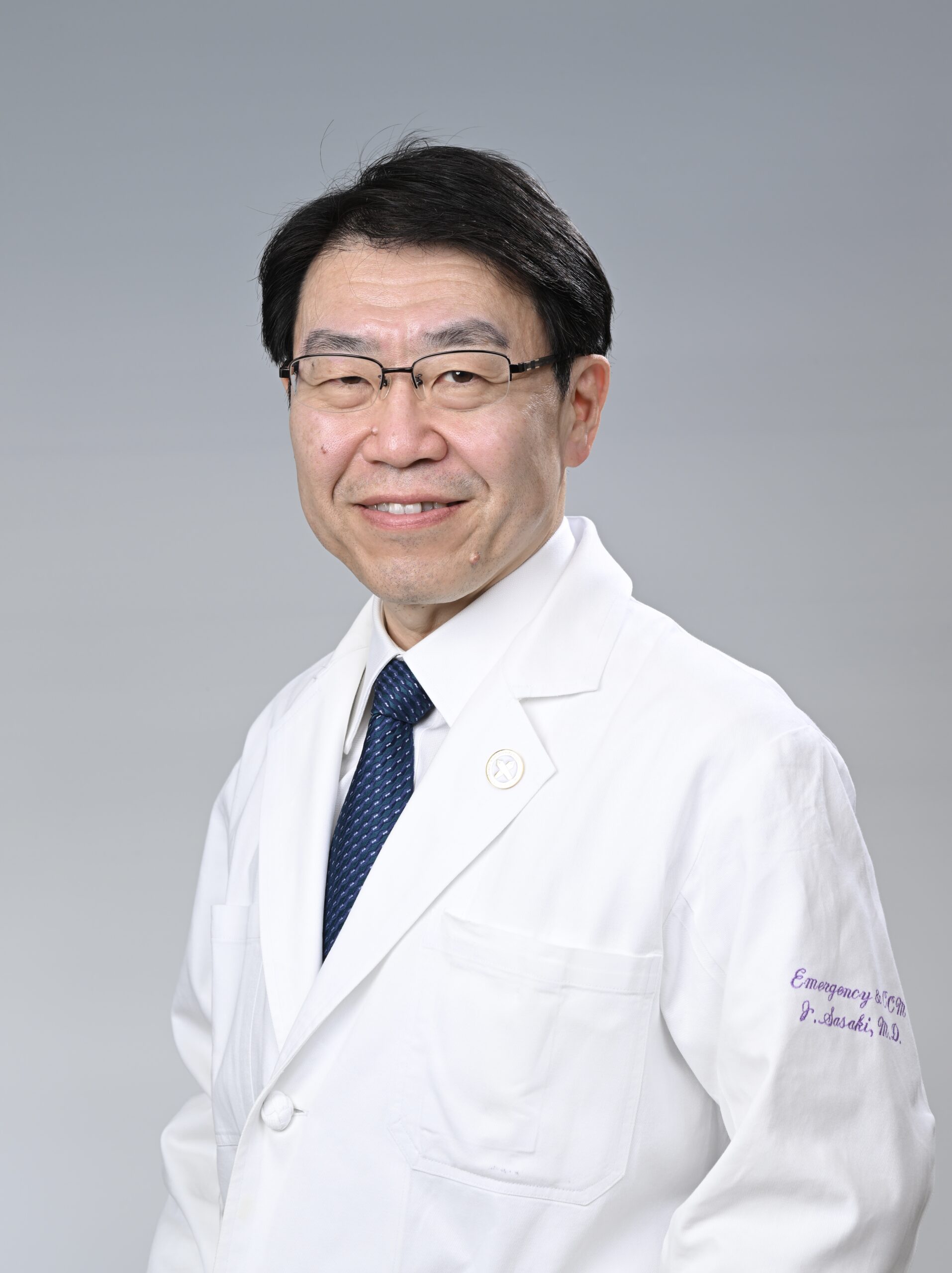
慶應義塾大学医学部救急医学 教授
慶應義塾大学病院 副病院長・救急科診療科部長
救急医療は、安全な社会生活を守るために欠かせない「セーフティー・ネット」の一部です。
救急科は救急医療に関する病院の窓口であり、救急車で搬送されるすべての患者さんの診療を担当します。救急外来には24時間体制で救急科専門医が常駐し、重症度や年齢に関わらず、病気や外傷・熱傷・中毒などまで幅広く救命医療を含めて診療を行える体制が整えられています。
診療の結果、各診療科の専門治療が必要な場合には、迅速に各診療科の医師と協力して治療を行います。入院を必要とする場合には、救急科を含め、病気の種類に応じた専門治療を考慮した適切な診療科に入院します。自力で救急外来を受診した患者さんには、看護師がトリアージを行い、各診療科の医師が中心になり対応します。
また、当院は東京都災害拠点病院の一つに指定され、日本DMAT(Disaster Medical Assistance Team: 災害派遣医療チーム)指定医療機関にもなっています。
2026年新年挨拶
救急医療は、社会の変化を最も鋭敏に反映する医療分野の一つです。ポストコロナの時代を迎えた現在も、救急・集中治療の現場には、重症化する患者、複雑化する病態、そして限られた資源の中での迅速かつ的確な意思決定が求められ続けています。当科では、外傷、熱傷、急性腹症、皮膚軟部組織感染症、急性中毒、心肺停止蘇生後、環境障害、敗血症性ショックといった重症患者を主診療科として受け入れるとともに、他診療科から依頼を受けた集中治療を要する傷病全般にも対応し、病院における高度急性期医療の中核を担ってまいりました。
こうした不確実性の高い医療環境において、我々が拠り所とすべきものは何か。その答えは、医療技術や設備だけではありません。医療人として決して忘れてはならない資質、すなわち未知に向き合い続ける知的好奇心(Curiosity)、情報やエビデンスを鵜呑みにせず本質を見極めるための批判的思考(Critical Thinking)、そして正しい情報を正しく社会や患者に伝えるためのコミュニケーション能力(Communication Skills)であると、私たちは考えています。情報が氾濫し、真偽の見極めが困難な時代だからこそ、これらの資質を組織として共有し、実践していくことが不可欠です。
救急医療は、平時のみならず、災害や社会的危機に直面した際にも、人々の生命と健康を守る「社会のセーフティーネット」として機能しなければなりません。アカデミアに身を置く我々には、目の前の患者を救うだけでなく、その経験を教育と研究へと昇華し、次の世代と社会に還元する責務があります。医学生や臨床研修医、救急・集中治療に携わる専攻医、さらには救急隊員に至るまで、多職種・多世代が学び合える場を提供することは、救急医療の持続可能性を支える重要な使命であると考えております。
2026年は、慶應救急としての存在意義をあらためて問い直し、社会に対して何を提供できるのか、何を誇り得るのかを明確に示す一年にしたいと考えています。診療・教育・研究のすべてにおいて質の向上を追求し、社会から信頼され、必要とされ続ける救急医療の実践を目指してまいります。本年も皆様のご理解とご支援を賜りますよう、心よりお願い申し上げます。
2026年(令和8年)1月
慶應義塾大学医学部救急医学
佐々木 淳一
これからの救急医に必要な
“3つのC + R”
救急医はよく「医の原点」と呼ばれていますが、その歴史は世代ごとに進化してきました。
昭和40年代頃、いわゆる交通戦争と呼ばれる車による事故が多発した社会で、外傷外科に特化した重症患者の診療にあたったのが「第1世代」。次いで、北米型ERの導入をきっかけとして、軽症も含めた1次~3次救急のすべてを診察するようになった「第2世代」。
さらに、従来のER型救急診療を基本としながらも、来院前のプレホスピタルから救急外来、集中治療室での重症患者の治療まで一貫して引き受けているのが我々「第3世代」ということなります。
そして現代、日本中のあらゆる病院に「救急科」が設置されて来ていることでも分かるように、外科や内科とともに救急医学の専門性が社会でも認知をされてきました。
これからの救急医療を担う第4世代には、幅広い社会のニーズへ対応しながら、いかに「セーフティー・ネット」になりえるか、が強く求められてくると思います。
そのために当科では、未来を見据えたプロフェッショナルな人材を育成するため「3つのC + R」というスローガンを掲げています。
- Cooperation 協働
救急現場ではチームで活動することが特に重要です。刻一刻と変化する状況の把握、他科との連携など、「協働」こそ救急医療の根幹を成すものです。 - Challenge 挑戦
従来のやり方に留まらず、新しい方法や新しい道を模索し、創造していくべきと考えます。常に社会の先導者という意識で「挑戦」し続けることです。 - Contribution 貢献
これからの救急医療はいかに社会のセーフティーネットとなりえるかが鍵となります。社会ニーズに応え、「貢献」出来る医師こそ我々の理想です。
+
- Resilience 回復力
今後は予測不可能な事態に遭遇することも予想されます。我々には変化する状況や予期せぬ出来事に対して、柔軟かつ上手に適応し、影響を低減し、迅速に回復する力が必要です。
《当科の紹介映像をご覧ください》